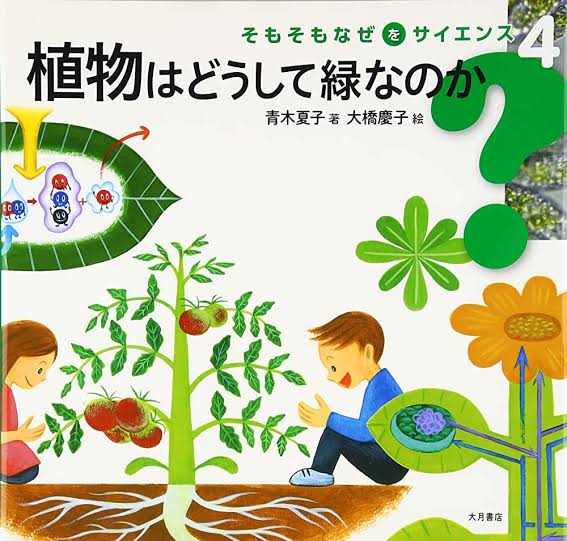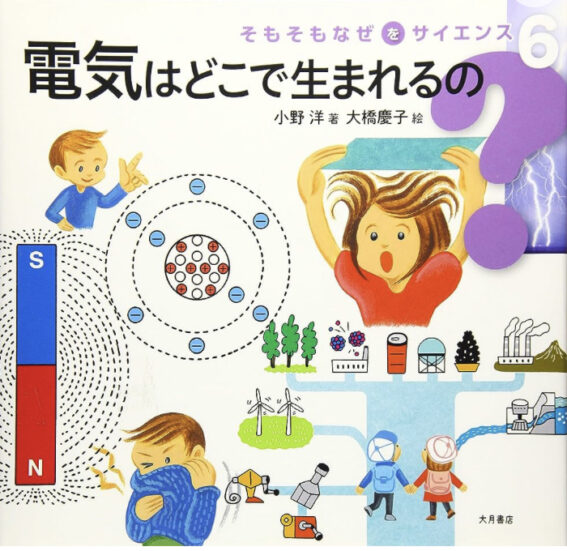そもそもなぜをサイエンス5
山崎 慶太 著 / 大橋 慶子 絵 大月書店
・科学や自然のふしぎが好き♡ or 解き明かしたい人♪
・天文宇宙検定の勉強をはじめる,している、もっと基礎力をつけたい人
・科学とか難しい…と拒否反応でやすい人
天文宇宙検定1級合格をめざして、理数系の基礎を小学生レベルから学び直していたら、ピッタリの絵本を見つけちゃいました (しかもシリーズもの♡)
同じような状況の方いるかな? いてもいなくても!(笑) 天文宇宙検定テキストの関連する級と章(2023年現在)も記載して、【そもそもなぜをサイエンス】シリーズまるごと、順々にご紹介します📖✨
ぜひこの本で、あなたの中にもある「なぜなぜ??をサイエンス」の知的好奇心を刺激してくれる、わくわくの世界をのぞいてみてください♪🧪⚗️🤩
目的
理数系の基礎つくりはもちろんのこと、
【そもそもなぜをサイエンス】シリーズも半分完読し後半戦に突入. ここまで来たらシリーズ制覇したい!✨と、シリーズ4まで読み終えて
地球上のすべての生物が頼っている、植物のとんでもないありがたさ(呼吸の原材料である有機物と酸素の両方)に、あらためて襟を正し、感謝の気持ちをもってもう少し意識的に向き合おうと思うなら
自然循環を知るためにやはり避けて通れない「菌類」😅苦手なんですが…
・自然循環の「全体像」を今よりもう少し細かく知る/苦手な部分を避けてきたゆえ(笑)
・天文宇宙検定2級10章に関連あり↓
・微生物等に詳しくなることで、宇宙生物学(アストロバイオロジー)にもっと好奇心がわくカモ 🦆
・私たちの遺伝情報や脳の働きを担うタンパク質やブドウ糖などの働きに興味を持つことで
↓ ↓ ↓
☆老化や体臭などの予防、若いうちからアンチエイジングの習慣化が楽にできるきっかけづくり
☆脳の活性化で、老若男女関係なく能力や才能の発揮→人生の豊かさへとつながるきっかけづくり
等になると感じ、表紙を見るだけで拒絶反応を起こしていた「食べ物はなぜくさるのか」の「カビ(菌類)」について、(苦手な画像の部分はなるべく観ないようにしながら)向き合ってみました ww🤪

目次
・食べものは、かならずくさる
・食べものは水と有機物でできている
・「くさる」とは食べものが別の有機物に変化すること
・くさるとくさいタンパク質
・食べものをくさらせる原因は細菌
・細菌がいなければくさらない ー パスツールの発見
・食べものをくさらせるもうひとつの原因 一カビ
・くさったものを食べたら、かならずおなかをこわす?
・くさっていなくてもおなかをこわす一食中毒
・くさっても食べられるもの
・コウジカビによる発酵一 米を甘酒に、大豆をみそに変える
・酵母菌は糖をアルコールに、乳酸菌は糖を乳酸に変える
・酸素も食べものをくさらせる
・くさる、さびる、老化 一 みんな酸化現象
・細菌やカビを殺し、酸素を取り除いて、くさらせない
・細菌やカビをふやさない工夫 – 干もの・冷蔵・くんせい
・生きている生物がくさらないわけ
・皮ふに1兆個、腸には1000兆個の細菌がいる
・もしも、細菌やカビがいなかったら
YUKA的コメント / 天文宇宙検定テキストとの関連
・食べものは、かならずくさる
「くさい(臭い)」は「くさる(腐る)」が語源という説明に
日本人が苦手とする香水などの強すぎる時の香りのことや、
体臭・老化現象におけるバクテリアやタンパク質などのバランス、
ストレスや多価不飽和脂肪酸、
内臓の弱まり、
私たち生物の五感や危険察知の野性本能
等を思い出しました
・食べものは水と有機物でできている
私たちがおもに食べている炭素・水素・酸素が結びついた「有機物」、水や食塩、二酸化炭素などの「無機物」については「人はなぜ酸素を吸うのか」P28 / 「植物はどうして緑なのか」P4~7,etc…にも詳細あり
・「くさる」とは食べものが別の有機物に変化すること Y目🍼🍖
・くさるとくさいタンパク質
タンパク質が(炭・水・酸)のほかに窒素・硫黄が結びついた有機物ということは知っていたが、腐ったときに肉や魚 vs 野菜や果物のにおいの差が「細胞壁」(cel炭)にあるとは!…😳オモシロイ 詳しくは本書を開いてみてね♪
・食べものをくさらせる原因は細菌
単細胞生物である細菌が20分/回、細胞分裂していく図を見て「ネットワークビジネス」や「家系図」を連想した人は他にもいるハズ🤭 いろいろな形の細菌が載っております.
・細菌がいなければくさらない ー パスツールの発見
レーウェンフックの自作顕微鏡に興味がわき🔬 1608年のリッペルヘイ(眼鏡職人/オランダ)望遠鏡の特許申請却下の話(天文宇宙テキスト3-7)を思い出しました.
1765年のスパランツァーニの実験で、この時代で既に食品の長期保存に大きな影響を与える検証結果が出ていたことにおどろき😲
・食べものをくさらせるもうひとつの原因ーカビ
いたってシンプルなカビの解説. 白カビの写真がかすみ草を連想させ、腐敗写真があっても、なんとか乗り切れたページ(笑)🌸
・くさったものを食べたら、かならずおなかをこわす? 🥟🫘🐉💧
くさったものを食べておなかをこわすのは細菌やカビを食べたからではないとは!😳
昔マクロビオテックを学んだ時、人の欲求と味覚などの五感(無意識の力)の関係について畏敬の念を抱きましたが、このページではそれらにプラスして、炒めたり茹でたりといった人間の知恵の素晴らしさにについて改めて意識できました✨
・くさっていなくてもおなかをこわす一食中毒
「腐敗菌」と「食中毒菌」の違い. 毎年、身近な人やNEWSで聞く食中毒. その原因5種類をシンプルな絵で解説してあり
NEWSを聞いたとき「またか」と流して終わらず、興味を持ち、予防のために自分の頭で深く考える基礎知識を授けてくれたページになりました.知識がないと予防できないですものね.
・くさっても食べられるもの
「腐敗」と「発酵」の違いを解説. 私自身も酵素や甘酒・ぬか漬けetc…を作りますし日本酒も好きですが🍶✨チョコレートが果実を発酵させていることを思い出し、製造工程に興味がわきました🍫✨
リサーチした情報 (軽め)


・コウジカビによる発酵一 米を甘酒に、大豆をみそに変える
現在、脳の唯一の栄養源と言われているブドウ糖. そのブドウ糖を主成分とする甘酒の作り方を紹介してくれています♪ ちなみに私は甘酒摂取をできるだけ長く続けられるように(習慣化)するため「発酵美人」で簡略化しています.
・酵母菌は糖をアルコールに、乳酸菌は糖を乳酸に変える
自分が死なない程度の濃さのエチルアルコールを周りに捨てブドウ糖をひとりじめするらしい酵母菌は単細胞生物とは思えない賢さだなと😳🧐✨ 昔「発酵」について学びたくて、大学リサーチした(だけ)ことのある者にとって楽しいページでした ww
・酸素も食べものをくさらせる
「くさる」現象の3パターン. 酸化が健康や老化に大きく関係していることは今やとても有名なお話しですが、緑茶の変化やペットボトルの容器の比較写真はとても分かりやすいです.「ペットボトルに入っているのになぜ中の物が変化するの?」と子供に聞かれて答えられない大人は必見のページ ww
・くさる、さびる、老化 一 みんな酸化現象
健康やアンチエイジングに興味ある人・取り組みたい人は、「何をしようか」の具体策の前に、先ず知っておくべき最低限の基礎の基礎知識.
・細菌やカビを殺し、酸素を取り除いて、くさらせない
ここまでで活性酸素について考察した後に読むこちらのページでは、できるだけ新鮮なものを選び・食べた方がよいと言われる理由がシンプルに分かります. タイトル通り、私たちの身近にあるくさらせないための手法の数々が紹介されていて、子どもとQ&Aしながら楽しめるページ.
・細菌やカビをふやさない工夫 – 干もの・冷蔵・くんせい 💤
植物が自分のからだを守るための物質(抗菌作用)や燻製についても説明があり、殺菌作用や香ばしい香りが400種類以上もふくまれる燻製の煙のお話はとても魅力的🍖✨
燻製つながりですが、昔「銀の匙 Silver Spoon」という映画を観て、あらゆる物事がどんどん簡略化され、真実を知らない、又は目をそらして生きていくことが当たり前に美化されている現代で、「なんとなく知っていること」と「この現実としっかり向き合い受け入れ生きていくことの大きな違い・大切さ」を、つくづく感じさせてくれる貴重な映画と出会えたなと、感じたことを思い出しました.
・生きている生物がくさらないわけ
私たちの身体が健康的に生命を維持するために、どれだけ素晴らしい働きをしているかということについて、すばらしくシンプルに解説してくれています.
私たち誰もが持つ承認欲求について考えてみれば、毎瞬毎瞬これだけの働きをし続けてくれている身体に対しての理解をすれば、身体を慈しむ気持ちや自己肯定の大切さを感じることができるかもしれませんね🐬
・皮ふに1兆個、腸には1000兆個の細菌がいる
↑上記に同じ
もしも、細菌やカビがいなかったら
学校で習った弱肉強食の食物連鎖. ここではカビや菌類などの有機物と無機物の側面からも説明してくれています.
以前「奇跡のリンゴ」で有名な木村秋則氏が「1㎝の土ができるのに100年かかる」とお話されていたのを思い出しあらためて調べてみたところ、これは日本における話で「早い」方なのだと. 海外には数千年で1㎝の所もあるそうです…😯😮💦
感想
こちらの本も特に何か問題提起などをしているわけでもなく、、ただただ、「食べ物はなぜくさるのか」のかについて淡々と書き綴られています。。が。が。が! 表紙を見ただけで「できることなら読みたくなーーーい‼🤣」「却下!😰」と、個人的に拒絶反応たっぷりのシリーズ⑤ (製作者様すみません🙏🏻 笑)
読み飛ばしたいほど苦手な項目と奮闘していた私ですが、ラストに近づくにつれ… 酵母菌や燻製などのお料理、体内細胞や自然循環の話へとめぐってゆき… 予想外に楽しめた内容でした📖✨
それでも「次はカビの写真出てくるかな?💦」とひやひやしながらページをめくっていく中、やっとおとずれてくれた【奥付】ページ… 🤣😝✨
「やっと終わったーーーー‼‼」
ヤッタ━━━ヾ(*≧∀≦*)ノ━━━!!!の解放感しかない✨ (すみません笑 / take2)
ヤッタ♪٩( ᐖ )و٩( ᐖ )وヤッタタ♪ ヤッタ♪٩( ᐖ )و٩( ᐖ )وヤッタタ♪
「ここ、天文宇宙検定テキストと関連するな~」とか「それについて、今まで全然考察したことがなかった!」「ここでこう話がつながるんだ!」など、これまでの人生で学んできた知識やこの先の天文宇宙検定に関連していく基礎となるお話が綴られているので、がんばって完読しました💮👏🏻💮👏🏻💮✨
が。 が。が。が。。。 いつも通り…
読めた・知ったことと(Input)、覚えていること・応用していけること(Output)は別問題なのでOutputのくり返しを… して.. するならば… するように ..てんてんてん …( -_-) 遠い目 … 笑+
ぜひあなたも手に取って、「細菌」や「植物」が織りなす不思議で魅力あふれる奇跡の数々、なぜ?なぜ?のわくわくの世界や答えを探してみてください📖✨
あなたなりの疑問や答えは、人生をさらなる充実へと、きっと導いてくれるから∗*゚✨
記憶定着のQ
☝
See you♡🐈