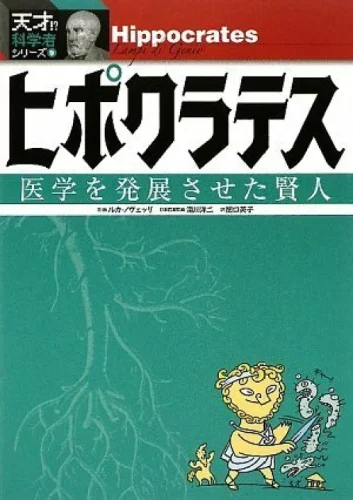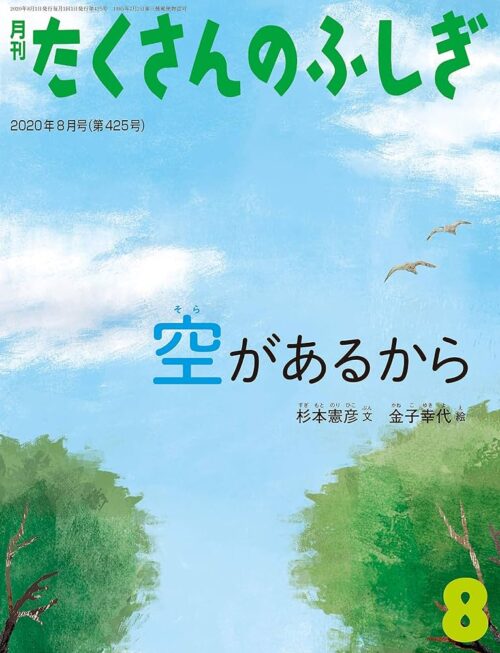天才⁉︎科学者シリーズ 10 エンドウ豆と遺伝の法則
ルカ・ノヴェッリ 文,絵 / 関口英子 訳 滝川洋二 日本語版監修
・生物学、遺伝に興味がある. 染色体とか気になる…
・科学の歴史とか…科学者とか…公式とか…覚えたいけど苦手. だけど好きになりたい
・天文宇宙検定の勉強をはじめる,している
・地学、理数系、自然の摂理などに興味がある
天文宇宙検定1級合格をめざして、理数系の基礎を小学生レベルから学び直していたら、ピッタリの絵本を見つけちゃいました (しかもシリーズもの♡) 第2弾‼
天文宇宙検定1級のテキスト読んでみても相変わらず「問」とか「演習」とか全く理解できず・ズ・zu …💀オワッタ の日々を送っておりますYukaLabo主. 📡⚗️
小学生レベルから始めればその物語や分かりやすさから、公式や定理に興味がでて少しずつでも理解が深まるのではないか…(1級受験はまだ遥か先のおはなし ww)
✨ きっと、こんなわたくしにも優しく理解をうながしてくれるのではないかと、淡い期待をこめ新しくGetしてきた小学生むけのこども本【天才⁉︎科学者シリーズ】
同じような状況の方いるかな? いてもいなくても!(笑) 【天才⁉︎科学者シリーズ】➀~⑩までまるごと、順々にご紹介します📖✨
ぜひこの本で、あなたの中にある知的好奇心を刺激して、「なぜ?どうして?」「それって本当⁉」「もっと知りたい♪」という、わくわくの世界をのぞいてみてください♪🧪⚗️🤩
ついに天才⁉︎科学者シリーズの最後の10冊目となる「メンデルのエンドウ豆と遺伝の法則」
でも「メンデル」と聞いても「ぺんてる(筆ペン)」が連想されてしまうわたくし.🖌 タイトルを見ても無知すぎて、正直何も心に響かなかったのですが… …読み進めてみると.と.と… あら素敵♡ 興味あふれる単語たちが並べつくされた大好きな世界でした✨
ということで. 今回は
メンデルは生物学の発見に統計学を用いた
若かりし頃うつ病を患っていた
ダーウィンがビーグル号で地球一周し「自然選択」を確信する頃、メンデルは小学生だった
現代では遺伝学の父と呼ばれるメンデルだが、その生涯は修道士(院長)で気象学者として有名だった
光学専門の物理学者クリスチャン・ドップラーの助手であった
などの発見がありました💡✨
※クリスチャン・ドップラーは天文宇宙検定2級の7章と10章「ドップラー効果」に出てきます.
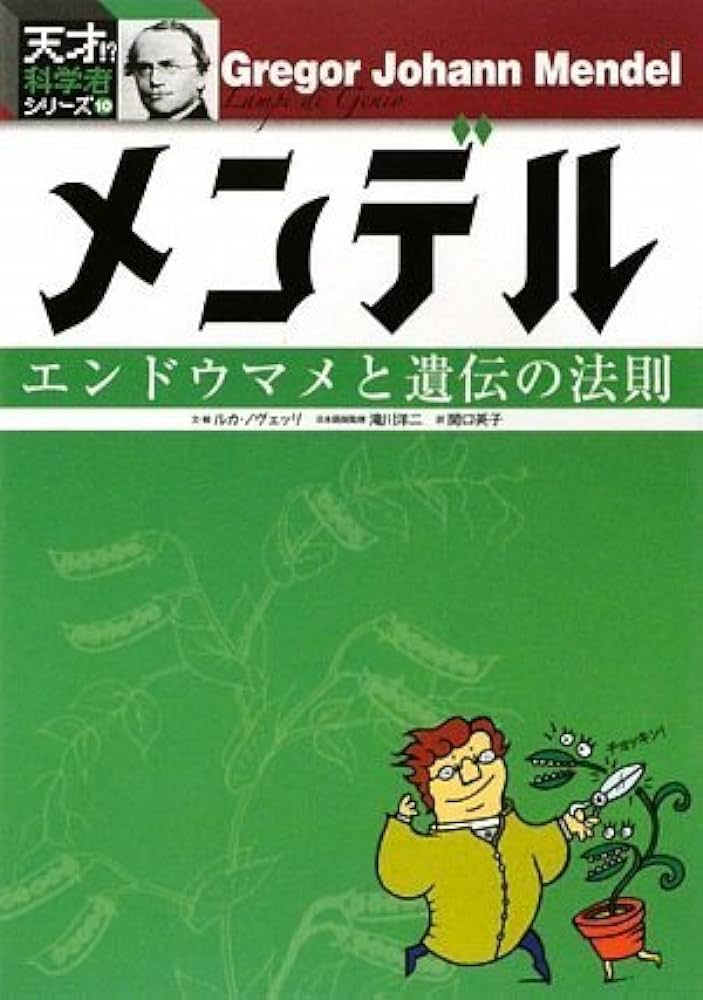
心ときめくメンデル用語集(P85~)
正直にもうしあげますと. 今回はメンデルの物語そのものより、P85~の「メンデル用語集」の方がうれしすぎました.┏(ε:)♥︎ペコリンチョ
こちらの「メンデル用語集」では、以前 そもそもなぜをサイエンス3「人はなぜ酸素を吸うのか」の記事でご紹介した「DNAの構造とはたらき ―DNA図書館へようこそ / 羽馬有紗 著」にも出てくるDNAやRNA・遺伝暗号や染色体・リボソームやヒトゲノムなどの単語の数々が紹介されており
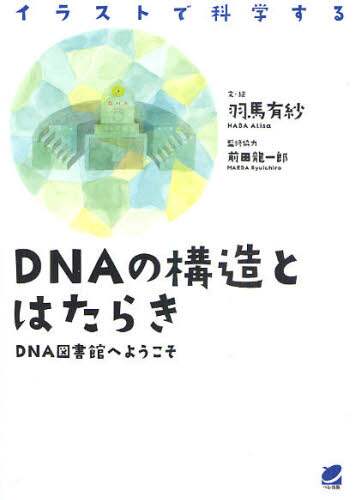
「DNAの構造とはたらき ―DNA図書館へようこそ 」📕と「そもそもなぜをサイエンス3 / 人はなぜ酸素を吸うのか」📘で学んだ知識が「メンデル」📗の理解を深めてくれ
また、「メンデル」のお話が、現代は当たり前に学校で教えてもらえる「DNAの構造とはたらき ―DNA図書館へようこそ 」と「そもそもなぜをサイエンス3 / 人はなぜ酸素を吸うのか」の知識として、明らかになっていくまでの歴史や内容の理解を深めてくれ一石三鳥の相乗効果ざんまいで楽しい時間となりました📖✨
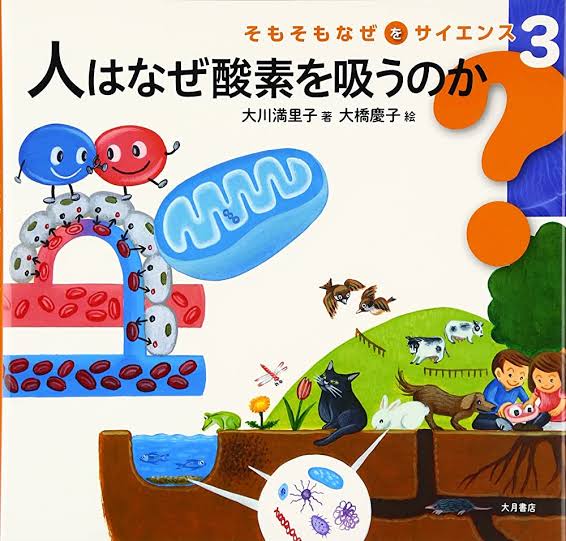
本書の「監修者より」に記載されている
メンデルの法則は、遺伝に規則性があることを示し、その後、その規則性を破る「突然変異」が起きることがわかり、ダーウィンの進化論をバックアップする理論になりました。さらに、遺伝子は染色体の発見で、より明らかになり、分子生物学の進歩によりDNAが解析され、くわしい遺伝のメカニズムが明らかになってきました。
監修者より P110 抜粋
↑の、大雑把な流れが
・「メンデル」
・「DNAの構造とはたらき ―DNA図書館へようこそ 」
・「そもそもなぜをサイエンス3 / 人はなぜ酸素を吸うのか」
の3冊でつかめたので、3冊まとめてもう一度再読しようと思います♪📚
天文宇宙検定2級10章の「宇宙における生命」がより理解しやすくなるかも🦆
メンデルの苦労
表紙のそで(折り返し)文章にある
この本には、メンデルが遺伝の法則を発見するまでの苦労や、さまざまなエピソード、ひらめきや悩みについて書かれています。
と案内のある通り、他の天才科学者シリーズの本よりも比較的「苦労や悩み」にフォーカスした表現ではあるなと感じましたが
・勉強を続けるためにブルノ修道院に入れた(ほかの修道院と少し違う)
・ブルノ修道院のシリル・ナップ修道院長は(メンデルがしたかった)自然科学を研究し、農村生活や農業をよくする方法として修道院を運営していた
・気のいい仲間にかこまれた生活
・2万冊の本がある図書室にピアノ、にぎやかなパーティーに革命家の友人
・奉仕の仕事が苦手で病気の発作が起こるので、研究と教師のみにしてもらえた
・食べることが大好きで、たくさん食べれていた
・ウィーン大学に留学させてもらえて、クリスチャン・ドップラーの助手をしたり、好きなエッティングスハウゼン教授の統計学を学び、助手として働いた
・正式な気象学者として認められ、有名になった
・ロンドン万国博覧会の視察に名乗り出て代表団のメンバーとしてヨーロッパを横断した
・自分をなぐさめるためにミツバチを飼ってみれば、ハチミツがモラヴィア、中央ヨーロッパの国々で知られ、モスクワにまで売られるようになった
・旅行をして法王に謁見したり、ヨーゼフ皇帝から勲章を授かった
などなどなど、、、本書を読む限りでは数多くの豊かさ・幸せも受けられていて、たしかに生前にメンデルの偉大な研究成果が認められることはなかったですが、決して不遇な人生ではなかったのだなと感じました✨
また、メンデルが亡くなってからではありますが、結果、ちゃんと功績が認められたことも運のよい人だなと. きっとそうでない埋もれている人が世の中にはたくさんいると思うので.
なぜメンデルの研究は理解されなかったのか
「どうしてメンデルの研究は当時理解されなかったのだろう?」と思い、最初は、両親と姉・妹の5人家族のメンデル. 優しい母&妹とは気が合うけれど、否定的な父と、いつも人を見張っているようなきびしい姉の言葉の数々に、感受性豊かなメンデルは自己嫌悪・自己否定が強化されうつ気味になり自己表現が苦手でそれが影響したのかな?と仮説を立てながら読み進めましたが
家庭教師のアルバイトもしていたし、ベルンのレアルシューレで非常勤の教員となった時の説明で「わたしは教えるのがとても好きだし、生徒にも人気がある」と記載あり、仮説は砕け散りました(笑). が、
巻末の「監修者より」の「内容だけでなく、方法も新しかったメンデルの研究」で、メンデルの研究が半世紀も理解されなかった理由(予想)のひとつが丁寧に説明されていて、納得できました👍
詳細をぜひ読んでみてください📖✨
時代背景
こちらのシリーズほぼ全ての本について言えることですが、最初に時代背景がかかれているので物語の内容が理解しやすくてたいへん助かります.
素人にはこの説明があるのと無いのでは、読み解くまでに大きな差がでるかと.
なお、こちらのシリーズは全部で10冊ありますが、それぞれの科学者が生きた時代順にならべると
⑨・④・⑧・①・⑦・⑥・②・⑩・⑤・③
となります。頭の中を整理させながら読みたい方は上記順番に読むのもおすすめです♪
See you♡🐈