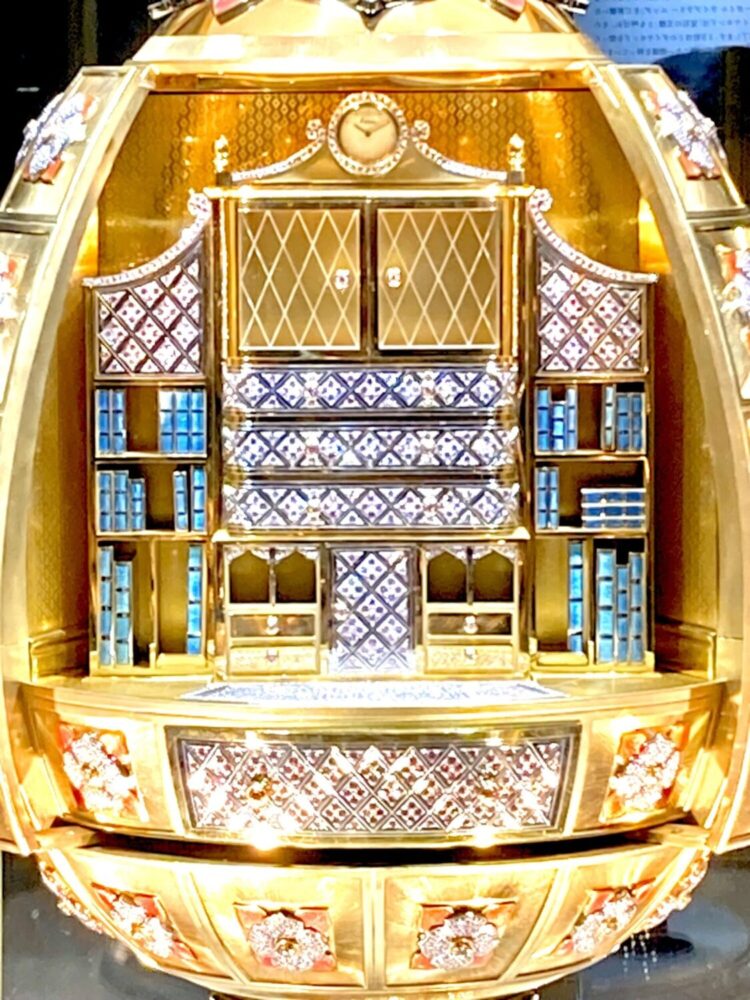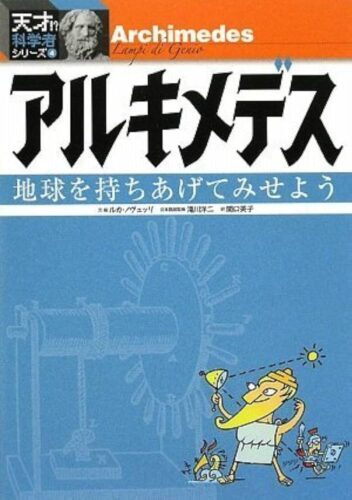天才⁉︎科学者シリーズ 3 ミクロの世界と宇宙のとびら
ルカ・ノヴェッリ 文,絵 / 関口英子 訳 滝川洋二 日本語版監修
・科学の歴史とか…科学者とか…公式とか…覚えたいけど苦手. だけど好きになりたい
・天文宇宙検定の勉強をはじめる,している
・地学、理数系、自然の摂理などに興味がある
天文宇宙検定1級合格をめざして、理数系の基礎を小学生レベルから学び直していたら、ピッタリの絵本を見つけちゃいました (しかもシリーズもの♡) 第2弾‼
天文宇宙検定1級のテキスト読んでみても相変わらず「問」とか「演習」とか全く理解できず・ズ・zu …💀オワッタ の日々を送っていながらも、あきらめず楽しんでおりますYukaLabo主. 📡⚗️
🦉難儀よのう…
✨きっと、こんなわたくしにも優しく科学の基礎理解をうながしてくれるのではないかと、淡い期待をこめ新しくGetしてきた小学生むけのこども本【天才⁉︎科学者シリーズ】
同じような状況の方いるかな? いてもいなくても!(笑) 【天才⁉︎科学者シリーズ】➀~⑩までまるごと、順々にご紹介します📖✨
ぜひこの本で、あなたの中にある知的好奇心を刺激して、「なぜ?どうして?」「それって本当⁉」「もっと知りたい♪」という、わくわくの世界をのぞいてみてください♪🧪⚗️🤩
このブログには便宜上【天才⁉︎科学者シリーズ】➀~⑩を順番に載せていますが、一番最初に出会った【天才⁉︎科学者シリーズ】はこの③のアインシュタインでした.
これまでアインシュタイン(というか、科学者系)の本を読んだことがなく、関連知識についてもほとんど知らなかったので、皆さんは当たり前にご存じのことばかりかもしれませんが
①発達の遅れを少し心配されるほど4歳になってもおしゃべりができず、9歳で適切な言葉を使って文章がつくれなかった
②5歳の時にはバッハもモーツアルトもバイオリンが上手に弾けた(言葉でなくイメージ思考?)
③特許局で技術専門職として働く(独創性,分野応用の見極め)とはどんな感じなのだろう?
④1922年のノーベル賞受賞理由は「光電効果の発見」だったのね
⑤アインシュタインの脳と眼球は今でもアメリカの研究機関で保存されている
などの発見がありました.
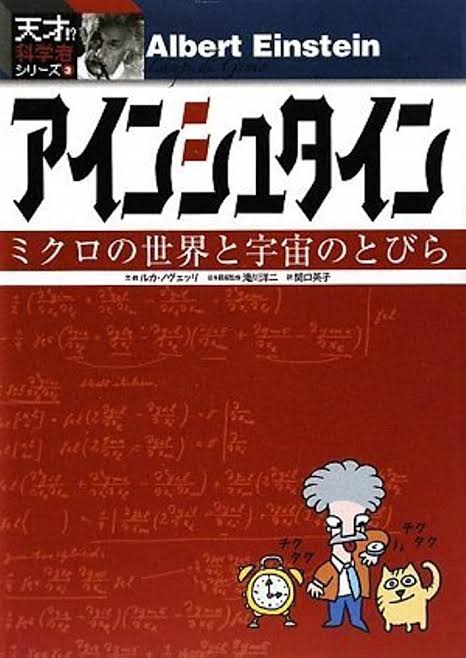
IQとEQ / EQの高さ
小学生のころに「なぜ科学者に対して興味がもてなかったか」と考えてみたところ、周囲の大人や頭の良いといわれる人たちを観ていて(細かいことは省きますが)「IQは高くても、EQ置き去りになってない?」と感じていたので、当時世間知らずで幼稚なわたくしは科学者というものに対しても偏見がありました. (/ω\)オハズカシイ…
が。。。成長と共に素晴らしい方たちに出合うたび「なんて繊細な感性と頭のよさをかねそなえた人なのだろう」とIQとEQのバランスの良さ・その繊細さに感嘆し、憧れるようになりました.
例えば、創元社発売の「AI〈人工知能〉のきほん」を引用するならば
コンピューターは1946年に初めて作られています。
その当時は、今のパソコンやスマートフォンのようになんでもできる機械ではなく、非常に単純なことしかできませんでした。例えば、今でいう電卓ぐらいのことしかできませんでした。
その電卓を見て、「これを使えば人工知能が作れる」と考えた人がいたのです。偉い人ってやっぱりすごいですよね。
AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ(1) AI〈人工知能〉のきほん P5より
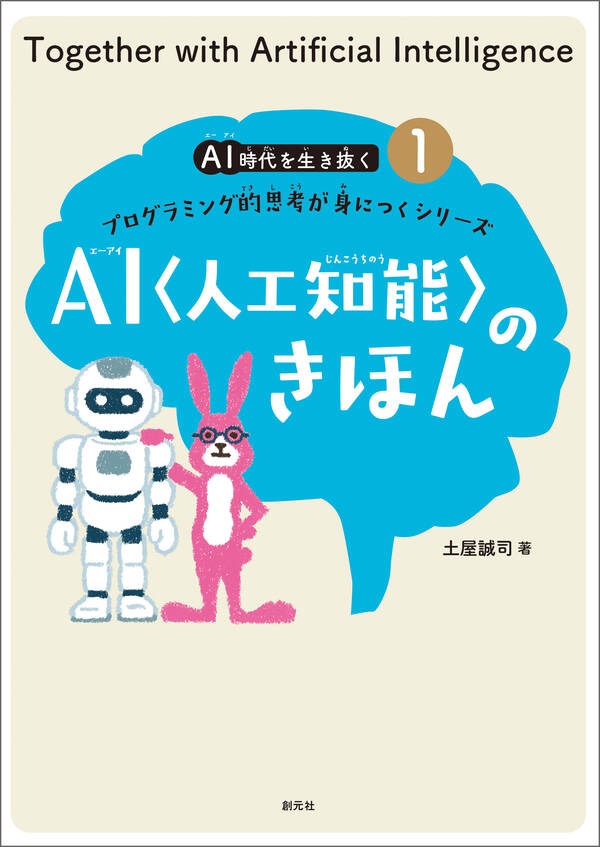
「電卓を見て、「これを使えば人工知能が作れる」と考えた人」のイメージ力・感性とはどれほどのものなのだろう?と想像してみるだけでわくわくしてきます✨
4歳になってもおしゃべりができず、9歳になっても適切な言葉を使って文章がつくれなかったけど、5歳の時にはバッハもモーツアルトもバイオリンが上手に弾け、積み木を使って複雑な形を作るのが得意だったアインシュタインの「卓越したIQとEQのバランス」に興味がわきました.
空想科学小説
本書の《はじめに》で
空想科学小説は誤解をまねくと言って、きらっていました。
じじつ、おおくのSF小説家が、アインシュタインの理論の根本的な意味をねじまげてしまったのです。
いっぽうで、適切な形での理論の普及には積極的でした。
と記載があり、まだアインシュタインの研究について詳しい知識を持ってないため「アインシュタインの理論の根本的な意味」ってなんだろう?と興味がわき
SF小説を読んだときに、そのお話がアインシュタインの理論にそっているのか、空想なのかを見極めながら読めるようになれたらおもしろいなと♪
歴史年表
基本的にアインシュタインの生い立ち・業績について事実を淡々と箇条書きのように記してあるだけなので、その理論もっと知りたい!と興味を持ち、深掘りしていくきっかけになるような説明やおもしろさは正直ありませんでした. その点が前作2冊とは違うなと.
実際、何回か読んでみてもなかなか頭に入らず、記憶に残っているのは「離婚した」「子連れと再婚した」「ノーベル賞の賞金を前妻と2人の息子にすべて渡した」という、全然研究とは関係ない世間話的なことばかりで(笑)😛+
ですが、が。
「興味は自分でつくるもの!」と意識を切り替えていきました☆
余談ですが. エンリコ・フェルミの名前が何回かでてきて、その度に
核物理学者のエンリコ・フェルミが1950年に、「宇宙人がおるんやて⁉ほなら、そいつらはどこにおんねん‼」と、おそらくイタリア語訛りの英語で問うたとされる。
そのため、宇宙人はいったいどこにいるのかという問いは、フェルミパラドックスと呼ばれている。
天文宇宙検定 公式テキスト2級 2021~2022ver P17より
という、天文宇宙検定テキスト2級のなかなか荒々しい文章を思い出して苦笑していました.
※新しい年のテキストでは削除されたようです.
なお、こちらのシリーズは全部で10冊ありますが、それぞれの科学者が生きた時代順にならべると
⑨・④・⑧・①・⑦・⑥・②・⑩・⑤・③
となります。頭の中を整理させながら読みたい方は上記順番に読むのもおすすめです♪
See you♡🐈