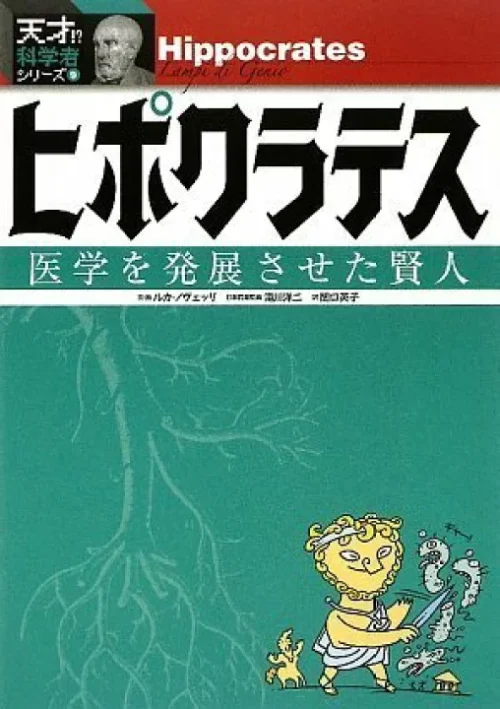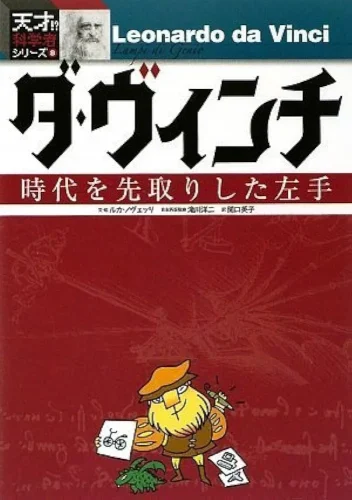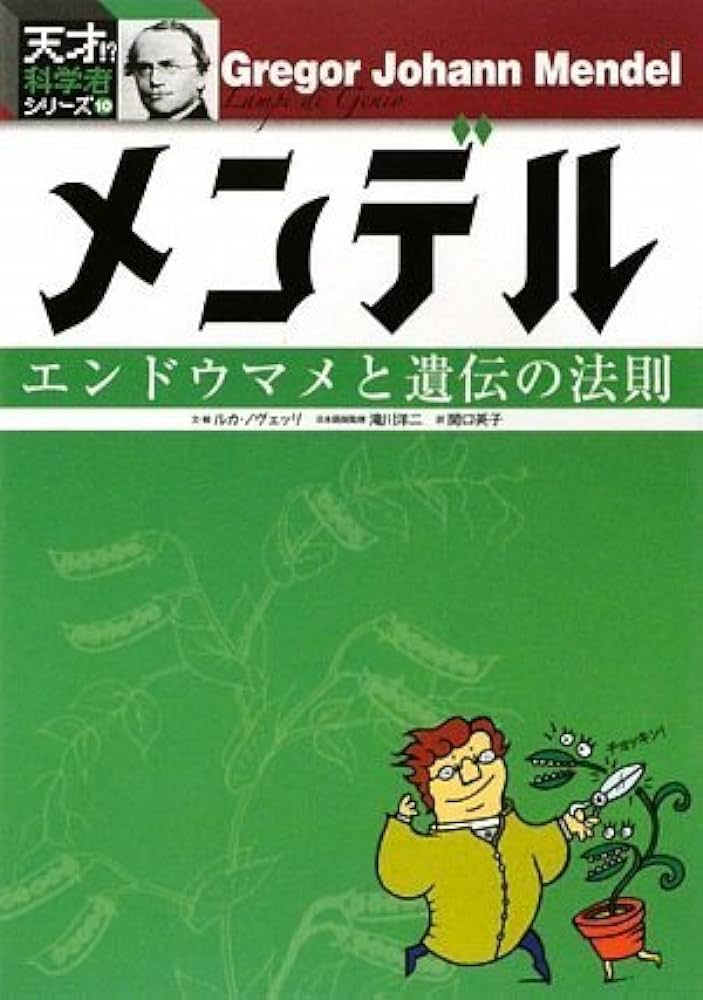天才⁉︎科学者シリーズ9 医学を発展させた賢人
ルカ・ノヴェッリ 文,絵 / 関口英子 訳 滝川洋二 日本語版監修
・科学の歴史とか…科学者とか…公式とか…覚えたいけど苦手. だけど好きになりたい
・天文宇宙検定の勉強をはじめる,している
・健康や医学、マクロビオティックや占星術・アーユルヴェーダなどに興味がある
・地学、理数系、自然の摂理などに興味がある
天文宇宙検定1級合格をめざして、理数系の基礎を小学生レベルから学び直していたら、ピッタリの絵本を見つけちゃいました (しかもシリーズもの♡) 第2弾‼
天文宇宙検定1級のテキスト読んでみても相変わらず「問」とか「演習」とか全く理解できず・ズ・zu …💀オワッタ の日々を送っていながらも、楽しんでおりますYukaLabo主. 📡⚗️
🦉難儀よのう…
✨ きっと、こんなわたくしにも優しく理解をうながしてくれるのではないかと、淡い期待をこめ新しくGetしてきた小学生むけのこども本【天才⁉︎科学者シリーズ】
同じような状況の方いるかな? いてもいなくても!(笑) 【天才⁉︎科学者シリーズ】➀~⑩までまるごと、順々にご紹介します📖✨
ぜひこの本で、あなたの中にある知的好奇心を刺激して、「なぜ?どうして?」「それって本当⁉」「もっと知りたい♪」という、わくわくの世界をのぞいてみてください♪🧪⚗️🤩
「ヒポクラテスって何の人だっけ?」なんとなく聞いたことがあるってことは、どこかで習ったのだろうが… 「医療関係の学校で【誓い】とか何とか…何か関係あった?なかった?」程度の知識しかなかったので、この本を読み
➀それまでの医術から迷信・呪術を切り離し、科学としての医療を発展させた
②たった1人の王の医者(莫大な量の金銀や名誉を約束)より万人の医者となることを選んだ. 後に「さすらいの医師」として大勢の弟子,手伝い,ロバたちと共に旅を続けた
③診察代金として金貨,銀貨を受け取ったが、貨幣のない人たちはお碗一杯の麦や「ありがとう」と言うのがせいいぱいという人もいて、ヒポクラテスはそれぞれの人が自分にできる形の支払いでいいという考えであった
④相手が誰であろうとその人の健康をとりもどすために最大限の努力をする. 半分以上は命の助からない病人でも、どのような出会いでもそこから何かを学び、すべての病の経緯を記録に取って後世に残した.
⑤笑う賢人デモクリトスと交流があった
などの発見があり、一言で表すなら「なかなか深みがあって好きだな」と感じ、ぜひこの記事を読んでいるあなたにも手に取ってみてほしいと思う一冊になりました.
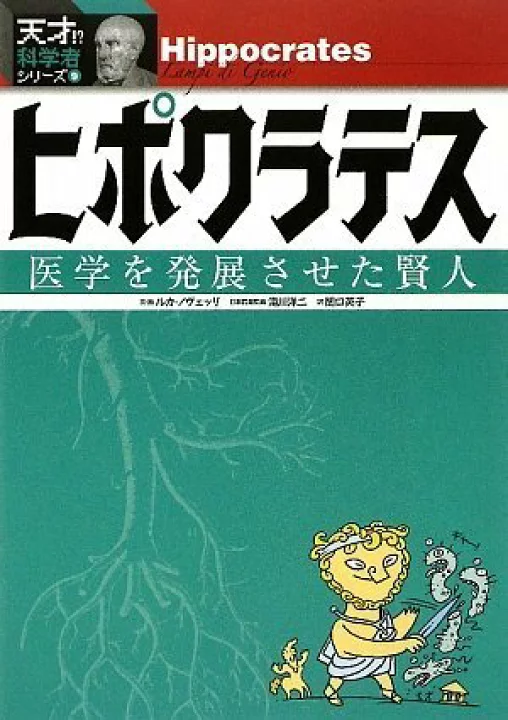
迷信・呪術を切り離し科学としての医療発展させた
・医学の神アスクレピオスの子孫とされる家系の父
・力と勇気の神ヘラクレスの子孫とされる家系の母のもとに生まれ
・祖父も父も叔父たち・いとこたちもみんな医師という、代々医術を施し神殿を管理してきた一族.
というコス島で最も高貴な家系のひとつとされるとても良い家柄で育ち、医師は神に仕えるものと考えられ神殿で行われる儀式にも参加しながら育ったというヒポクラテスが、どのようないきさつで人々から尊敬される優秀な医師の父に対し「物事に対して疑問をいだかない」と感じ
ピタゴラスやタレス・アナクシメネス・アナクシマンドロス・ヘラクレイトス・エンペドクレスといった「知恵を愛する人」たちと同じように、神にまつわる伝説とは一定の距離を置き、身のまわりで起こる自然現象を理論的に観察し、様々な問いかけを行なえるようになっていったのか? その過程に興味がわきました.
こちらの本を読む限りでは、父に対し「物事に対して疑問をいだかない」と感じ、神にまつわる伝説とは一定の距離を置き、腹痛を治すのに神々の力にすがる必要はないと合理性を主張したヒポクラテスが
莫大な量の金銀や名誉を約束されても、たった1人の王の医者より万人の医者となることを選んだり、自分の限界を自覚しながらも、どのような相手でも丁寧な診察で真剣に治療し、アスクレピアデスの子孫だけが医師になれるとされる古代ギリシア時代に、多くの弟子を迎えたりした
その根底には、もしかしたら感受性豊かな若かりし頃に観てきた、皆から尊敬される父の患者が完治していく様子を喜びそうでない時の悲しむ姿が、ヒポクラテスの心に根付いていたからなのかもしれないな…と想像をふくらませていきました.
また、後半に紹介されていくヒポクラテスの医術を読んでいくと、マクロビオティックの世界観や一物全体(食のことだけを指すのではなく、聞くもの見るもの身に付けるもの環境etc… 身のまわり全て・バランスを指す)と似ているな…と感じました.
全体という側面からは
運動という側面からは
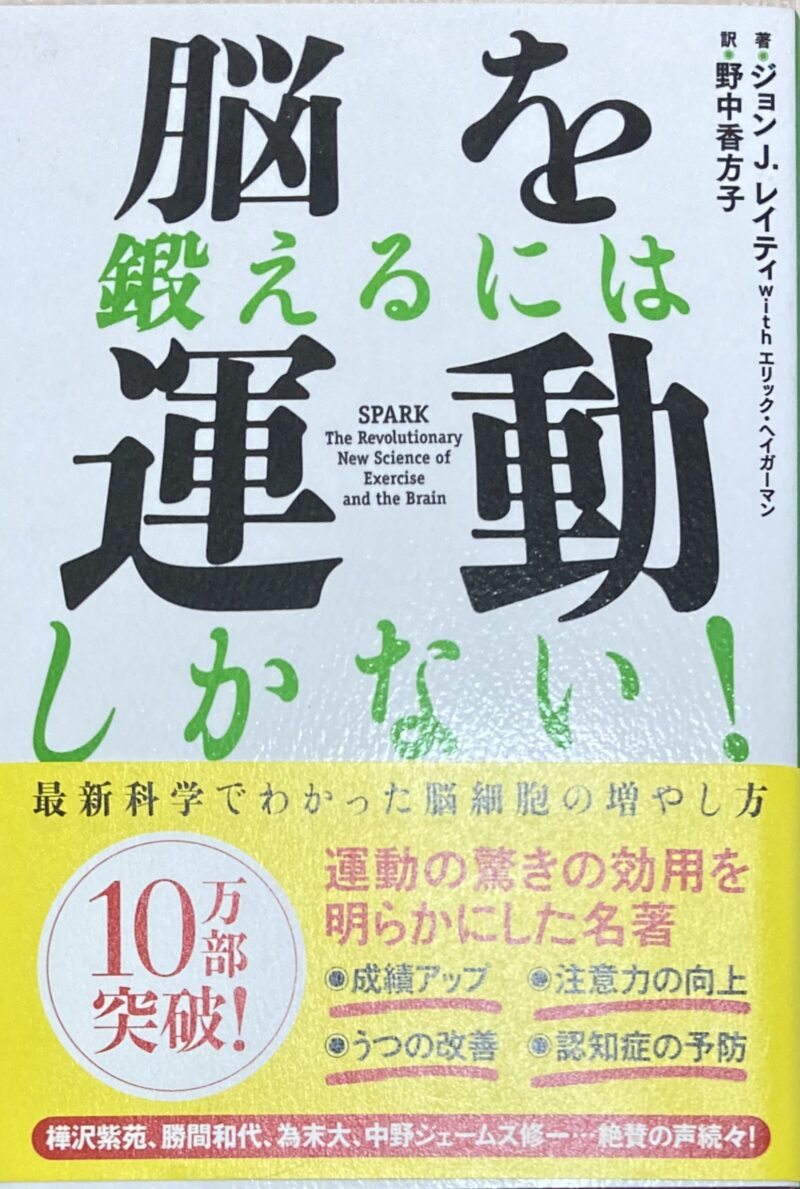
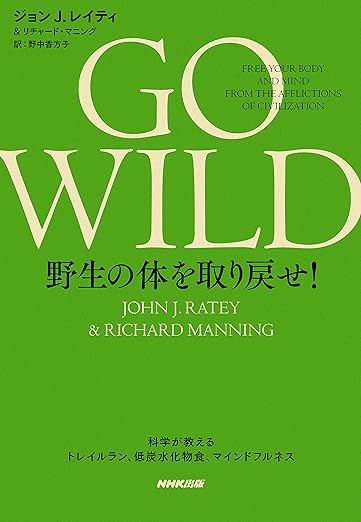
も面白いのでおすすめです♪
血液の循環
ちょっと引用の連打にはなりますが.
瀉血=治療の目的で、患者の血液の一部を静脈から取りのぞくこと(中略)ヒポクラテスは病人の体力がおとろえると言って、これに反対していた。
ヒポクラテス 用語集P94より抜粋
解剖学=(中略)ヒポクラテスの時代、人の体を八つ裂きにしたり、ばらばらにしたりすることは、しばしばあったが、研究を目的として解剖がおこなわれることは、ほとんどなかった。
P90より抜粋
とあるのに
ヒポクラテスの時代には、血液が体の中を循環していることも、まだ知られていませんでした。イギリス人の医師、ハーヴェイが血液の循環を発見するのは、何世紀もあとのことです。
P38より抜粋
という解説が、「研究を目的として解剖がおこなわれることはほとんど無いにしても、戦争があったり、八つ裂きやばらばらにすることがあるのに、なぜ血液が循環していることを知らないのか?」と、既に血液が循環していることを知っている現代に生きている私には想像が難しく、🧐🤔
心臓、脳、肺、腎臓、神経、神経組織、といったものがあることを知っていた。静脈と動脈の違いがあることもわかっていた。だが、それらがなんの役に立つのか、どのように機能しているのかは、まったくわからなかった。
ヒポクラテス P69より抜粋
「静脈と動脈の違いがあることもわかっていたのに循環していると考えていないのはなせ?なぜ?なぜ?」「では瀉血とはどのような考えで行われていたのだろう?」と、ヒポクラテスの時代の血液に対する定義が???でいっぱいで、「これは子供の様なまっさらな心と柔軟性がないと私には想像できないだろうな…」💣と感じるので、今後、自分の凝り固まった思考をほぐしていくのが楽しみです+📝💉
世界三大伝統医学
●古くから発展した医術として5000年前に活躍した中国の大帝「神農」につての記載(P18コラム/P97用語集)や
●「四体液説」「四大元素説」(P30,P33コラム/P107用語集)の、現代の占星術などにも使われている要素
●エジプト医学についての記載(P31~)があり
昔学んだマクロビオティックやアロマ・占星術や東洋医学との要素的関連性を感じるのですが、歴史性や横のつながりが分からず「世界最古 医術」とネット検索してみると、
「世界三大伝統医学」=ユナニ医学・アーユルヴェーダ・中国医学にたどり着き、「世界三大伝統医学」という存在を知りました「これってもしかして満月・新月ぐらい世間の常識なのだろうか?」と思いつつも、世の中(日本)で満月と新月があることをご存じない大人とも、これまで多々出会ってきたので、医療について知識のない私の発見も何かの役に立つかも?と思い記録.
また、占星術は天文宇宙検定3級で出てきますが、テキストには
ガリレオやケプラーのような王侯貴族専属の天文学者はほぼ例外なく、雇い主たちのホロスコープ(占星天宮図)を作成する占星術師でもあった。
天文宇宙検定3級テキストより抜粋
とあり、ヒポクラテス(本書)に占星術の説明はありませんが「四体液説」「四大元素説」の超シンプルなお話は、天文宇宙検定の記憶の関連付けに役立つかも.🦆
エジプト医学とミイラ
6.エジプトの医学(P31~)ではエジプトの医師の腕のすばらしさが記載されているのですが、その中に「彼らは人間の遺体を何千年も保存できる、特別な塩のつくり方を知っていた」とあり
「何千年も保存できる」って、改めて考えてみるととてつもなく凄いことだよな…と.「ミイラ作りに塩が使われていた」ことや「特別な塩とは?」という疑問からエジプト医学について興味がわきました✩⃛∗*゚😃なに🤩なに⁈😳ワク🤓わく+✨
エジプト医学にしても、数百種類もの薬物や治療法や医師の役割を書き記した神農の医術にしても、「5000年前にどこまでわかっていたのだろう?」「どうやって分かったのだろう?」と考えると… …
とりま、国立国会図書館に引きこもりたくなる & 海外旅行へ飛び立ちたくなる.·˖*✩⡱
で,,,,,, 好奇心に火が付くと日常生活を破壊してしまうYukaLabo主なので(笑)、この辺で気持ちと思考をセーブしておこうと思いますww
✈✨ ✈✨ ✈✨
🛫✨ 🛫✨ 🛫✨ 👻fu~あぶねえ…
時代背景
こちらのシリーズほぼ全ての本について言えることですが、最初に時代背景がかかれているので物語の内容が理解しやすくてたいへん助かります.
素人にはこの説明があるのと無いのでは、読み解くまでに大きな差がでるかと.
なお、こちらのシリーズは全部で10冊ありますが、それぞれの科学者が生きた時代順にならべると
⑨・④・⑧・➀・⑦・⑥・②・⑩・⑤・③
となります。頭の中を整理させながら読みたい方は上記順番に読むのもおすすめです♪
See you♡🐈